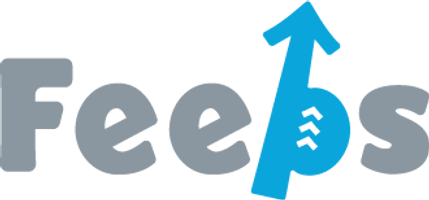“まず聴くだけ”から人は育つ!傾聴がつくる心理的安全性とチームの力
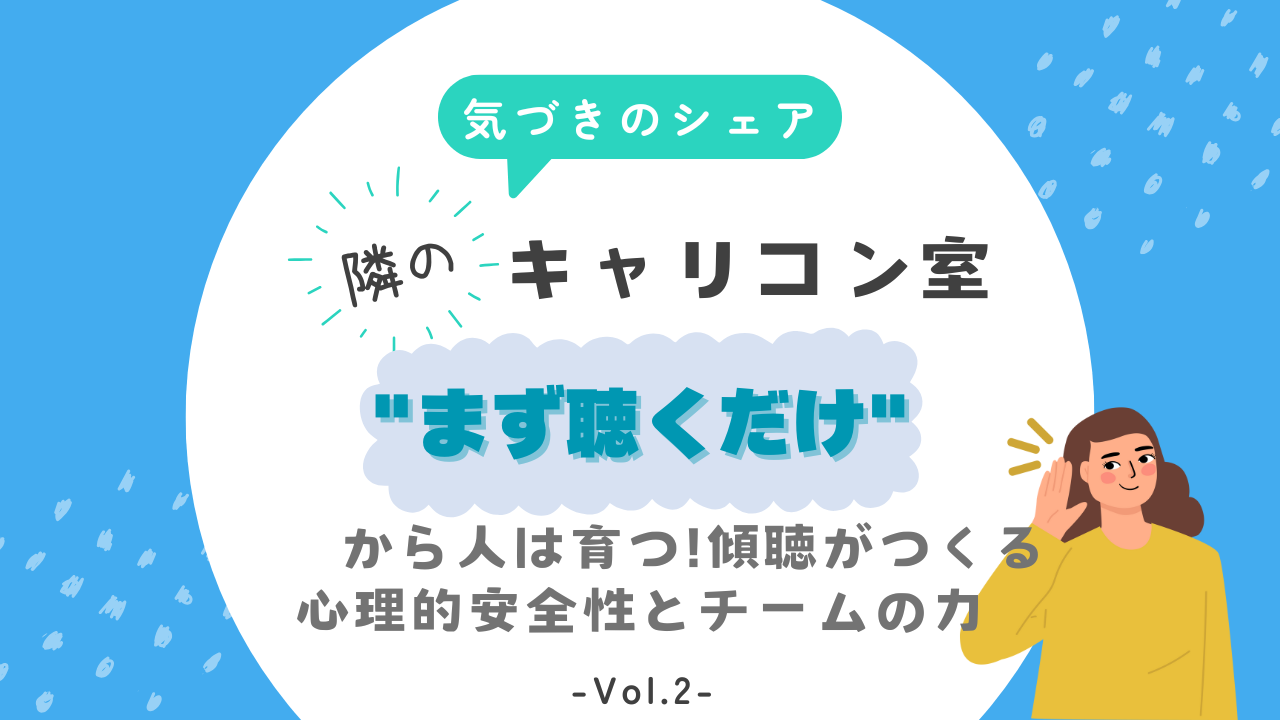
前回の記事で紹介した「若手エンジニアの5つの壁」。それを乗り越えるための環境づくりに“傾聴”の文化がとても重要だということがわかりましたね。
「話を聞くことが大事」と頭ではわかっていても、実際にどう聴けばいいのかは、意外と難しいものですよね。
本記事では、聴くだけでも効果を発揮する傾聴について、そのマインド・スタンス、そして得られる効果を解説します。
- 今、「教える上司」より「寄り添う上司」が求められている背景
- “まず聞くだけ”でも部下との関係性が変わる
- 聴く文化は、部下だけでなくリーダー自身にも様々な効果がある
- 今日からできる”3分間”で小さく傾聴を実践する方法
今「寄り添い型の上司」が求められる時代です
孤立しやすい働き方で「教える上司」より「寄り添う上司」が求められる

近年のリモートワークやプロジェクト単位の働き方の普及により、エンジニアが孤立しやすい傾向が強まっていますよね。そんな中で、部下との「関係性」をいかに築けるかが、育成や定着に大きく影響していると言われいます。
Googleが社内で行った大規模な研究「プロジェクト・アリストテレス」※1 は、“優秀な個人が集まることよりも、どのようにチームが機能するか” が成果を決めるという事実を明らかにしました。
特に最も重要とされたのが「心理的安全性」だと示されました。つまり、安心して意見や質問ができる環境があるチームほど成果を出しやすいということがわかったようです。
加えて、信頼性・構造と明確さ・仕事の意味・仕事のインパクトという5つの要素が揃うことで、チームは最大の力を発揮できると結論づけられました。
これは、上司が“寄り添い型”であるほど実現しやすいといわれています。
指示を出すだけではなく、メンバー一人ひとりの声に耳を傾け、安心して話せる雰囲気が、心理的安全性を育みます。まさに傾聴力ですよね!
たとえ意見が違っても「大丈夫、まずは話してみていいんだ」と思える空気があれば、人は自然と信頼し合い、自分の役割や仕事の意味も見えてくるのだと思います。
“そのままの自分”を受け入れてもらえることは、良い仕事に繋がり、成果になって返ってきます。
参考:
傾聴に必要な3つのマインドセットを確認してみましょう
- 評価しない:相手の話を「違う」「そんな考えでは」とジャッジしない。まずは受け止めることが自己開示を促します。
- 共感を意識する:第一声「それは大変でしたね」と添えるだけで、理解された感覚が生まれ、信頼関係が深まります。
- 正解を探さない:すぐにアドバイスを返すのではなく、「どう感じた?」「他に考えはある?」と問いかけることで思考が広がります。
さて、日頃の皆さんのマインドはいかがでしょうか?
上司という立場にあると、どうしても部下の話を“ジャッジする姿勢”で聞いてしまいがちですよね。それは、過去の経験から「同じ失敗を繰り返してほしくない」という思いがあるからこそだと思います。
そんな「失敗をさせたくない」思いから、ついジャッジやアドバイスを優先してしまいがちです。
けれども、それでは部下の考える力を狭めてしまうことも。
むしろ、失敗も成長の一歩と捉え、挑戦を見守るマインドこそ、傾聴にふさわしい姿勢といえます。
▼失敗したくない部下へ。代表からのメッセージ
“まず聴くだけ”でも変わる、部下との関係性

まずは、「ただ聴く」だけでも効果があります。傾聴とか細かいことが難しい!と思った場合は、”まずは聴く”を意識してみるだけで変化を感じます。
「心理的安全性」をつくる上司の態度など”受け止め力”にあり
エンジニアは、感情よりも論理で会話する傾向が強く、時系列に沿って結論から述べることが求められる場面も多いです。けれども、それと同じくらい「安心して感情を出せる場」があることも大切ですよね。
さて、それはどんな環境でしょうか?
- 失敗や不安を話しても否定されない:たとえばミス報告に対して「それはまずかった」ではなく、「気づけてよかった」と返ってくる。
- 沈黙も許される空気感がある:部下が言葉を選んでいる時間を尊重し、沈黙を恐れず、「この間も意味がある」と待ってもらえる。
- 何気ない雑談ができる:業務以外の会話が自然とできる関係性が、本音を引き出す土台になる。
- 意見を受け入れてもらえる:話の途中で口を挟まず、「なるほど、そう思ったんだね」と伝え返す。
聴く文化はリーダー自身にも効果として返ってくる
傾聴は「部下のためのスキル」と思われがちですが、実はリーダー自身にとっても大きなメリットがあります。
- 信頼の積み重ね
部下から「この人は自分の話をちゃんと聴いてくれる」という評価を得ることで、信頼度が高まります。信頼があるからこそ、部下は相談を早めに持ちかけ、トラブルも未然に防げるようになります。 - 余計な衝突や誤解が減る
「自分の意見が理解されている」という実感を持った部下は、防御的にならず、建設的な議論に臨めるようになります。結果として無駄な衝突が減り、チーム全体のストレスも軽減されます。 - マネジメントが楽になる
傾聴によって部下の本音や考えを引き出せると、リーダーが一方的に背負っていた課題解決の負荷が分散されます。メンバーが自発的に動き出すため、マネジメントの負担そのものが軽くなるのです。
つまり「聴くこと」は、部下の育成だけでなく、リーダー自身がより楽に成果を出せる環境を整える行為でもあるのです。
今日からできる”3分間”で傾聴を体験してみましょう
「傾聴」と聞くと、構えすぎて難しく、億劫に感じられるかもしれません。でも実はほんの小さな一歩からトライできるんです。
おすすめは、一日ひとり、3分間だけ“評価せずにただ聴く”時間を持つことから始めてみましょう!
- 朝の雑談で「最近どう?」と聞いて、最後まで遮らずに聴く。
- 打ち合わせ後に「率直にどう感じた?」と一言添えて、返答をジャッジせずに受け止める。
その3分間は「正しい答えを探す」ことをやめ、ただ耳と心を相手に向ける時間にしてみましょう。
人は誰しも話を聞いてもらうだけで、スッキリしたり、心が軽くなるなどポジティブな影響を与えます。
最初は小さな変化でも、「安心して話せるんだ」という経験が部下の中に積み重なることで、心理的安全性が少しずつ広がっていきます。
それが、チーム全体に波及し、発言が活発になり、信頼関係が強まり、成果へとつながっていく…。
その起点は、ほんの数分の「聴く時間」から始まります。
まとめ
- 「教える上司」より「寄り添う上司」は心理的安全性で効果が出せる
- “まず聞くだけ”でも部下との関係性が変わる
- 聴く文化は、部下だけでなくリーダー自身にもストレス軽減など効果がある
- 今日からできる”3分間”で小さく傾聴をスタートできる