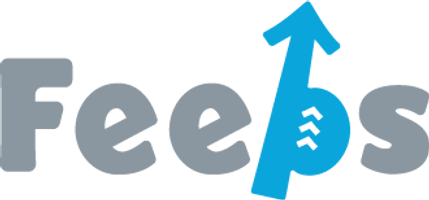管理職に“経営マインド”を持ってもらうには?
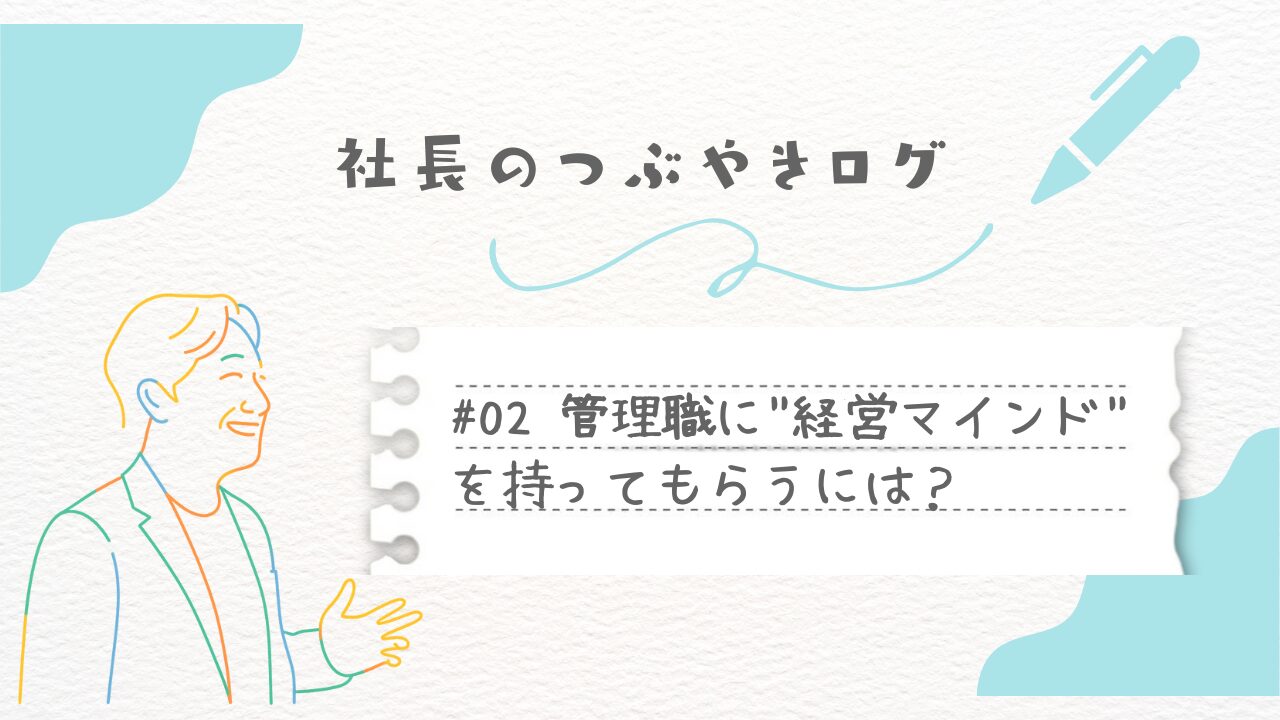
「もっと当事者意識を持ってほしい」
「管理職にも経営の視点を持ってほしい」
組織を動かしていると、こんな思いが湧いてくること、ありますよね。
でも、“経営マインドを持て”って言っただけじゃ伝わらないのが現実だったりします。
今回は、そんな悩みに少しでもヒントになるように、
「管理職に経営マインドを育てるには?」というテーマでお話ししてみます。
そもそも“経営マインド”って何?
まず大前提として、「経営マインド=数字を意識すること」ではありません。
それだけだと、コスト削減やKPIのチェックだけに終わってしまいます。
ここで言う“経営マインド”とは、例えばこんな感覚です。
- 自部署だけじゃなく、全体のバランスを見て判断する
- 目先の数字だけでなく、中長期の成長も見据える
- やる・やらないの判断基準を自分で持っている
ようは、「会社を一緒につくる側として考えて動ける」こと。
この視点があるかどうかで、日々の判断がまるで変わってくるんです。
経営マインドを“言葉”ではなく“体験”で育てよう
「視座を上げろ」「経営の視点を持て」
……って、言いたくなるんですが、なかなか伝わりにくいんですよね。
じゃあどうするかというと、体験を通じて気づいてもらうのが一番です。
【ステップ1】まずは「数字に触れる」機会を
たとえば、管理職にもPL(損益計算書)を一部共有したり、
自部署の利益構造を説明したりしてみてください。
最初はピンと来なくても、「この業務ってこんなに原価がかかってたのか」とか
「粗利は出てても利益は出てなかったんだ…」なんて気づきが、じわじわ効いてきます。
【ステップ2】意思決定の裏側を見せる・考えさせる
経営層がどんな判断をしているか、普段は見えないものです。
だから、「この意思決定にはこんな背景があるんだよ」と話すだけでも大きな学びになります。
さらに効果的なのは、経営判断をシミュレーションしてもらうこと。
「君ならこの場面、どう決断する?」という問いを投げて、一緒に考えてみましょう。
【ステップ3】成功体験をつくる
経営マインドって、“分かったつもり”だけではなかなか身につきません。
「自分で考えて動いた結果、ちゃんと成果が出た」
この実感があると、行動が変わってくるんです。
たとえば、コスト意識を持って取り組んだ業務改善が評価された、
他部門との横連携でプロジェクトを成功させた――
そうした経験は、自信と視座を同時に引き上げてくれます。
最後に:育てるのは“知識”よりも“視点”
「経営マインドを持て」と言って持てるなら、誰も苦労しません。
大事なのは、“考え方のスイッチ”を入れるきっかけをつくること。
それには、言葉よりも体験・気づき・納得感が効きます。
小さな成功を一緒に喜び、
迷ったときは「会社全体から見るとどうだろう?」と問いかけてみる。
そんな日々の積み重ねが、
「経営を一緒に担う仲間」をつくっていくのだと思います。